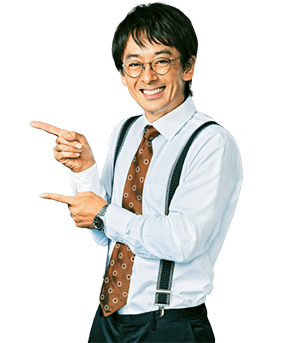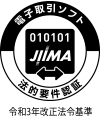システム開発の原価管理で重要なこと|よくある課題や効率化の方法

こんにちは!「楽楽販売」コラム担当です。
システム開発において重要な管理項目の一つに「原価」があります。原価とは、商品・サービスの仕入れや製造、販売などにかかる費用のことです。一般的に、特定の製品の製造に直接関わる費用を「直接費」、複数の製品にまたがって製造に関わる費用を「間接費」と呼びます。自社の原価を把握するためには、多数の費用を分類して内訳を明らかにする必要があります。
システム開発の原価管理業務では、間接費の配賦計算の工数が多いなど、課題を抱えている企業が少なくありません。管理業務に時間と手間がかかっている場合、効率的に取り組むにはどのような方法が考えられるのでしょうか。ここからは、システム開発の原価管理の重要性や、よくある課題、効率化の方法までお伝えします。
詳しく知りたい方はこちら!
この記事の目次
システム開発の原価管理に関する基礎知識
初めに、システム開発の原価管理に関する基礎知識をお伝えします。原価管理の重要性を改めて確認した上で、自社の課題解決の方法を検討してみましょう。
システム開発の原価管理とは
原価管理業務には、売上に含まれる原価を正確に把握する目的があります。企業が利益を最大化するために取り組む業務の一つです。原価管理には「総合原価管理」「個別原価管理」「標準原価管理」といったさまざまな手法があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 総合原価管理…一定期間における製品一つあたりの原価を計算する方法
- 個別原価管理…プロジェクト別に原価を計算する方法
- 標準原価管理…原価を理論的に算出する方法
システム開発の場合、原価管理は「個別原価管理」によって行われるケースが多くなっています。
一般的な原価管理についての詳細は、以下の関連記事で解説しています。基礎知識を確認したい方は、こちらも併せてチェックしてみましょう。
関連記事はこちら 原価とは?おさえておきたい原価に関する基礎知識
関連記事はこちら 原価管理の基礎知識|必要な理由や管理の流れ、課題の改善法とは
システム開発でかかる原価の例
一般的に、システム開発における原価の大部分を占めるのは、エンジニアやプロジェクトマネージャーの給与などの労務費です。そのほかに、システム開発を行うIT企業では主に以下のような原価が発生します。ここでは、システム開発会社における原価の具体例をご紹介します。
| 原価の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 労務費(人件費) | 直接費:エンジニアの給与、プロジェクトマネージャーの給与、デザイナーの給与 など 間接費:バックオフィス部門の従業員の給与 など |
| 経費 | 直接費:サーバー費用、ライセンス費用、機器の購入費用、通信費、従業員の交通費 など 間接費:光熱費 など |
| 外注費 | 直接費:外注先のシステム開発費用、サーバー保守費用、デザイン費用 など |
システム開発で原価管理を行う重要性
システム開発プロジェクトの利益を最大化するには、支出の無駄をなくす必要があります。そのためにも、原価を可視化して、状況に合わせてコントロールすることが大切です。原価管理に取り組むことで、コストを効率的に調整、削減することができます。こうした理由から、原価管理はプロジェクト管理に不可欠だといえるでしょう。
システム開発の原価管理におけるよくある課題
システム開発の原価管理では、以下のようなさまざまな課題を抱えている企業が少なくありません。ここでは、多くの企業で見られる課題をご紹介します。
原価の細かな内訳を管理する必要がある
システム開発における原価の内訳は、プロジェクト単位で変わります。そのため、案件ごとに直接費と間接費を適切に割り当てる作業に多くの工数がかかるのが課題です。なかでも、間接費を配賦(はいふ)して割り当てる「配賦計算」は、複雑で難しい作業となります。
売上に複数の原価を紐づけて管理する必要がある
システム開発の原価管理では、各プロジェクトの売上に複数の原価を紐づけて、詳細な管理を行う手間がかかります。また、その上でリアルタイムでの収支管理を行い、プロジェクトの評価を行わなければなりません。こうした背景から、管理業務が煩雑になりやすいといえます。
複数のプロジェクトの原価管理を同時に行う必要がある
社内で複数のプロジェクトが進行している場合、上記で触れた原価管理の業務を同時進行する必要があります。件数が多くなるほど、より業務が煩雑になる傾向にあります。リソースが不足し、現場の担当者の業務負担が増加しやすい点が課題です。これにともない計算ミスの発生も懸念されます。万が一、原価管理でミスが発生すれば、予算達成にも影響を与えかねません。ミスを避けるためにも対策が求められます。
システム開発の原価管理を効率化する方法
システム開発の原価管理業務では、エクセル(Excel)やGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトを使って入力する方法もあります。ただし、管理するプロジェクトの件数が多い場合はソフトの動作が重くなり、管理上のストレスが増える点がデメリットだといえるでしょう。こうした理由から、原価管理の効率を向上するなら専用の「原価管理システム」を活用するのが効果的です。
原価管理システムには、複雑な原価計算を自動化する便利な機能が搭載されています。また、原価を含む収支管理や、差異の分析も簡単にできる仕組みとなっています。このように原価管理に特化した機能が充実している点が表計算ソフトとの大きな違いです。
原価管理システムを導入するには、初期費用や月額利用料金などの一定のコストが発生します。ただし、上記の業務効率化の効果が期待できることからコストメリットが高く、長期的な観点では費用対効果が高くなるのが魅力です。
システム開発で使いやすい原価管理システムを選ぶポイントとして、大きく以下の2点が挙げられます。
- 複雑な配賦計算に対応できるか?
計算の対応範囲が広く、自社の業務に合わせて柔軟にカスタマイズできると理想的です。 - プロジェクト単位の管理が可能か?
プロジェクト別の詳細な管理にも対応可能で、自社の規模に適したシステムが望ましいでしょう。
システム開発における原価管理には、業務効率化による課題解決が期待できる専用システムを活用してはいかがでしょうか。
システム開発の原価管理は専用システムで効率化しましょう!
ここまで、システム開発における原価管理の重要性や、よくある課題、効率化の方法などの情報をお伝えしました。原価管理業務には、プロジェクトの原価を適切に管理して利益を最大化するという重要な役割があります。しかし、管理業務ではプロジェクト単位で原価を割り当てたり、複数プロジェクトの原価を同時に管理したりするため非常に多くの手間がかかります。これらの業務を効率化するなら、原価管理に特化した機能が搭載された「原価管理システム」を活用するとよいでしょう。なかでもおすすめなのは、クラウド型販売管理システムの「楽楽販売」です。
「楽楽販売」には、プロジェクトごとの収支を自動計算する便利な機能が搭載されています。複数の原価を売上に紐づけて集計でき、リアルタイムで現状を確認できるのが魅力です。そのため、原価率の悪化にも早期に気づきやすく、プロジェクトが赤字になるリスクを未然に避けるために役立ちます。さらに、「楽楽販売」は自社のオペレーションに合わせて管理項目や表示内容を柔軟にカスタマイズすることが可能です。サポート体制が充実しているので、システムの導入前から運用まで一貫したフォローを受けられます。
「楽楽販売」はシステム開発といった小規模の原価管理に対応できる機能性と柔軟性のあるシステムです。機能や導入メリットについて、詳しくは以下のページでダウンロードできる資料でご紹介しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
詳しく知りたい方はこちら!
この記事を読んだ方におすすめ!
記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽販売」コラム編集部
- 「楽楽販売」のコラムでは販売管理・受発注管理・プロジェクト管理などをはじめとする、あらゆる社内業務の効率化・自動化の例をご紹介していきます!